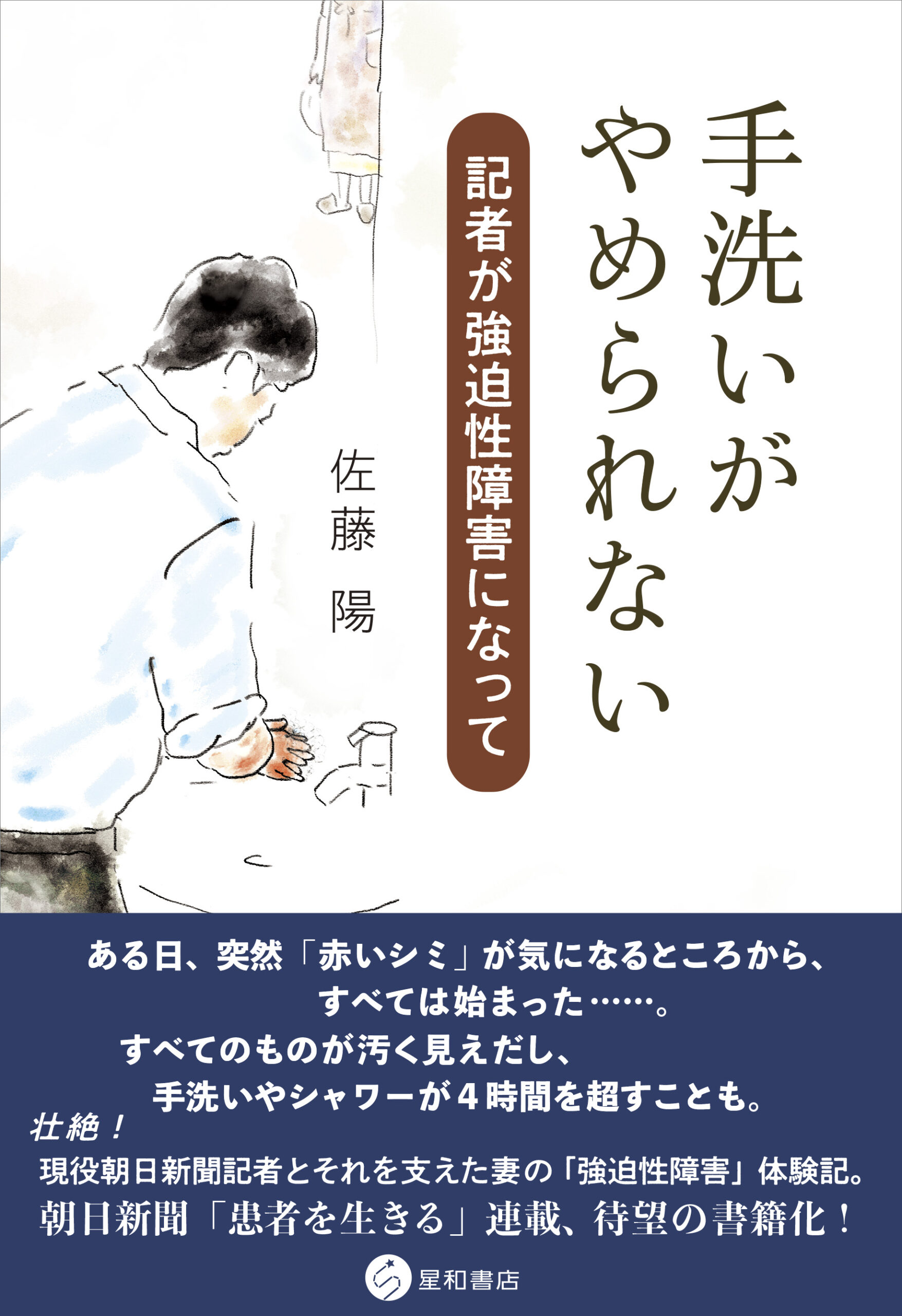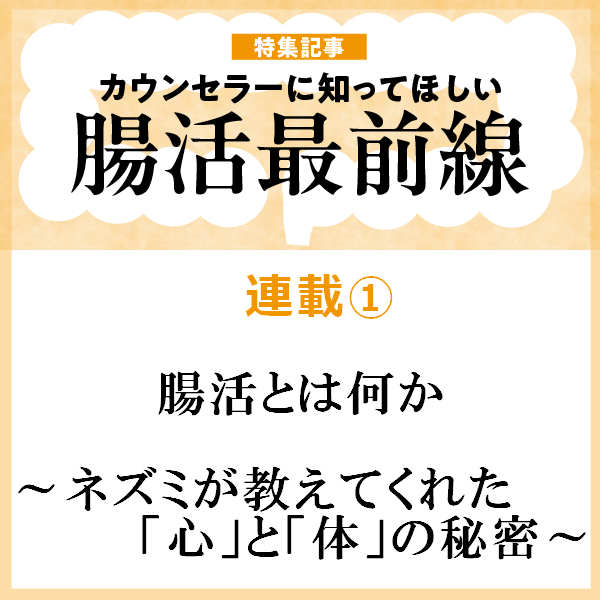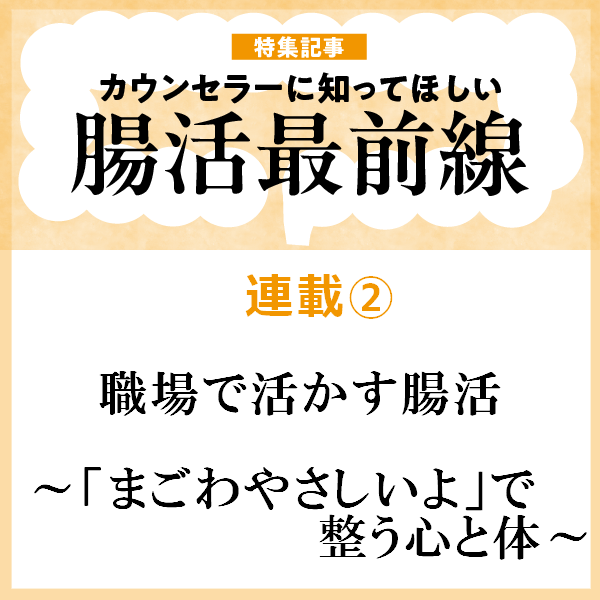| 強迫性障害(OCD)という病気をご存じでしょうか。日本の有病率は欧米と同様に人口の2~3%と、うつ病よりは低いですが、統合失調症より高く、決して珍しい病気ではありません。世界保健機関(WHO)は、生活上の機能障害をひきおこす10大疾患の1つに挙げています。 この病気に30年来向き合ってこられた朝日新聞記者の佐藤陽さんに2回にわたりご執筆をいただきます。 |
突然気になりだした「赤いシミ」 そこから始まった不安と絶望の日々
私は現在、朝日新聞の記者をしている。いまは「普通」に働いているが、20年ちょっと前は、「普通」に働けない時期があった。心の病に冒されていたのである。強迫性障害という病気だ。本コーナーでは2回に分けて、病気と闘い乗り越えた体験、その後の仕事や生活などについて書きたいと思う。
1993年ごろのことだろうか。突然、道路の「赤いシミ」が気になり始めた。朝日新聞に入社し、最初の任地・大分に赴任して2年ほどたったころだった。当時日本で初めてのエイズ患者が報告されていた。血液などから感染するため、「赤い物」が気になりだしたのだ。
もちろん、血液を踏んだだけでは、エイズに感染することは絶対ないことはわかっていた。でも、もしかしたら、何かの拍子に体の傷口から、それが付着することがあるのではないか、と考えてしまった。
どんどん広がる「汚い対象物」
その後、「汚い対象物」は、どんどん広がっていった。道端に落ちているつばやシミ、トイレに垂れているおしっこ……。それらを直接踏んでいなくても、「もしかしたら踏んだかも」と思うと、気持ち悪くなり、手洗いにつながっていった。
94年に岐阜、95年に名古屋へ異動した。みんなが汚く見えだした。同僚の手が赤ギレしていると気になってしまう。足を組んでいる人がいると、気になってしょうがなかった。地面から少しでも離れるようにと、腕を上に上げて歩くようになった。
家に帰ると、せきを切ったように手を洗った。30分、1時間、1時間半……どんどん時間も長くなっていった。シャワーの時間も、延びていった。仕事にも支障が出てきた。

そんな生活を送りながらも、96年1月、いまの妻と結婚した。僕の症状を知っていた妻は「結婚して、一緒に治そう」と言ってくれた。うれしかった。
しかし、結婚生活の始まりは、ひどいものだった。妻の助言もあり、96年春ごろ、当時いた名古屋市の精神科クリニックを受診した。そこで、正式に「強迫性障害(当時は強迫神経症)」という診断を受けた。
薬を飲んで少し改善した感じもあったが、副作用が怖くて薬はすぐやめてしまった。症状はあまり良くならなかった。あるとき妻に「もう治療はやめたい」と言った。すると、妻は泣きながら「じゃあ、いまのままでいいの?」と反論した。
そんなとき、「森田療法」という日本独自の精神療法があることを知った。基本、薬は使わない、ということで、関心をもった。森田療法を使い神経症を治そうという自助グループがあり、参加してみることにした。
参加すると、強迫性障害ではないが、対人恐怖や不完全恐怖などさまざまな神経症の人たちがいた。僕が自分の体験を話すと、我がことのように聞いてくれた。とても心強かった。「やはり経験者は違う」と感じた。
自助グループでのある先輩の言葉が、いまも心に残っている。「手洗いを区切って、後ろ髪を引かれる思いで、次の行動に移ろう」「少しでもできた事実を評価しよう」。体験者の言葉なだけに、僕の心に響いた。
東京転勤で症状は悪化の一途
ところが98年、東京転勤が決まり、また状況が悪化の一途をたどる。人が多く、「気になること」が格段に増えたのだ。東京本社で働くというプレッシャーものしかかった。パワハラの上司もいた。ここであまり良くなかったのは、自分の心の病体験から、メンタルヘルスの取材を始めたことだ。たとえば、うつ病の人の取材であれば、相手に共感しすぎて、自分自身のメンタルに支障を来すようになってきた。
手洗いやシャワーの時間は合わせて、4~5時間ほどになった。会社に行けず、家で引きこもる日もあった。いまだから言えるが、「取材です」とウソをついて、家にいたこともある。とにかく外に出て、「汚い物」にふれるのが怖かった。
外のトイレも使えなかったため、やむなくオムツをして会社に行くようになった。オムツに用を足してしまい、ビチョビチョになり、おむつの替えを妻に持ってきてもらうこともあった。また、そんなビチョビチョの状態の時に、上司から「緊急の記者会見に行け」と言われ、行ったこともある。いま考えると、よく耐えたな、と我ながら感心する。
当時を振り返って、妻は「何かにとりつかれた感じだった。表情もなかった」と話す。妻も治そうと必死で、クリニックの受診やカウンセリングには、必ずついてきてくれた。会社に行くのを渋ったときも、布団を引っぺがし、「会社に行かないと、外に出ないと、ダメになっちゃうよ」と、家から出してくれた。強迫性障害の場合、うつ病などと違い、そっとしておくことは逆効果なことも多いそうだ。
「何で俺だけ、こんな目に遭うんだ」。僕は、生きることすら嫌になってきていた。「俺はこのまま廃人になってしまうのか」。不安と絶望にうちひしがれた日々だった。

 |
佐藤 陽(さとう・よう)
1967年生まれ。91年朝日新聞社入社。大分支局、生活部、横浜総局などを経て、文化部(be編集部)記者。医療・介護問題に関心があり、超高齢化の現場を歩き続けてまとめた著書『日本で老いて死ぬということ』(朝日新聞出版)がある。近著は、様々な看取りのケースを取り上げた『看取りのプロに学ぶ 幸せな逝き方』(朝日新聞出版)。妻と娘2人、オス猫2匹と暮らす。妻はK-POPにハマり、看護師と大学生の娘たちも反抗期。慕ってくれるのは猫の「ジャッキー」と「きなこ」だけ。趣味は、愛猫と戯れることと、韓国ドラマを見て号泣すること。数年前から、世のおじさんたちを元気にする「おじさんプロジェクト」を立ち上げた。その一環として、プロのラッパーに弟子入りし、ラップを始め、ライブも行った。現在、フェイスブック番組「ゆるおじLIVE」を継続中。2007年より、早稲田大学理工学術院非常勤講師として、講義「産業社会のメンタルヘルス」を担当。 |
著書:『手洗いがやめられない 記者が強迫性障害になって』(星和書店 2023年)